01・12月モンゴルからの留学生:ナンディンエルデネさん/01・10月グラフィックデザイナー:レイリー・モンタージさん/01・6月 キャリアアップを目指して転職 徐京淑さん/01・4月 インド家庭料理の店を経営 クンナさん/01・3月 中国・西安で写真展を開催 細川和昭さん/01・2月 上海から友好の使者 郭盛麟さん/
2001年12月モンゴルからの留学生:ナンディンエルデネさん
〜日本の漢字はおもしろい 交流に役立つ仕事もしたい〜

「馬乳酒は体にいいんですよ、ホントいくら飲んでも酔うっていうことはありませんね。ぜひ飲んでくださいよ」と、のっけから馬乳酒の話になってしまった。日本で相撲取りになっているモンゴル人は馬乳酒をよく飲んでいる地域出身だとか、馬が食べる草の栄養がそのまま体に伝わるからかな、なんていう風に馬乳酒のことをニコニコしながら話してくれたのはナンディンエルデネさん。モンゴルから今年9月にやってきて、大阪で日本語を学んでいる。
27歳のナンディンエルデネさんはモンゴルの首都ウランバートルの出身。モンゴル国立外国語大学で日本語を学んでいたが、卒業後はあまり日本語を使う機会がなく、せっかく覚えた漢字なども忘れかけていたそうだ。もともと貿易の仕事に興味もあったし、日本とモンゴルの交流にせっかく覚えた日本語を使いたいという希望もあり、日本に留学することに決めた。
実はナンディンエルデネさんは一人っ子。日本へ来るのに両親は反対しなかったんですかと尋ねると、自分で生きる路を探すことは必要だと反対はしなかったそうだ。息子に期待することが大きいからかなとも語るが、いずれにしても日本での新たな生活は始まった。
勉強はもちろん忙しいが、夜の食事は宿舎の留学生会館で自分で作る。モンゴル人は大の肉好きで、羊のイメージがあるかもしれないけれど好物は牛肉とのこと。でもやはり値段が高くて野菜が多いときも良くある。昼食は日本のご飯と定食が好物だ。私費留学生なので、できるならアルバイトもしたい。しかしなかなか見つからないとのこと。「ある時アルバイト募集という店に入っていって申し込んだけれど、留学生は使っていないということで断られました」と経験を語る。
しかしそんなことではめげていられない。日本の冬はどうですかと尋ねると、外は寒くないけど中は少し寒いかな、という返事。ウランバートルでは真冬には気温が零下25度くらいになる。雪も降る。だけど湿気が少なくさらさらの雪だから汚れることもなく、子供の頃から外で遊んでいた。ウランバートルは標高1350メートルの盆地で、高くはないけれど周辺に山がある。冬には山へ行っていつもそり遊びなどをしていた。
そのかわり家へ戻るとお湯を使ったセントラルヒーティングで部屋はぽかぽかしている。窓も2重だから半そでのTシャツで充分に過ごせる。そんな生活を送ってきたから、日本では外では寒いと感じないけれど、部屋の中にいる時は気を付けないとTシャツ姿で気づかずに風邪をひきそうになることもある。
これからの目標はまずとにかく語学を磨いていくことだという。そして経済の勉強も。「中学生の頃から数学は余り得意でなかったんですよ。だから語学系を選んだということになるんですが、やっぱりそれだけではダメだから理系のほうも努力します」。むつかしいことにあえて挑みたいという熱意はその笑顔の中からもよく伝わってきた。
2001年10月グラフィックデザイナー:レイリー・モンタージさん
〜日本で生きるのが自然 仕事をするのが大好き〜

レイリー・モンタージさん、イラン人だったと紹介すべきかも知れない。祖父が第二次大戦後すぐに日本に来て生活を始めた。貿易関係の仕事をしていた父は祖父に勧められて母と9ヶ月の姉を連れて日本にやってきた。レイリーさんはそのあと1956年に夙川市で生まれたので、日本生まれの日本育ちということになる。イランの首都テヘランに住んでいた祖父も父も宗教的にはイスラム教徒ではなくバハイ教徒だったので、日本といういわば新天地で生きていくことを選んだのだそうだ。
「今年の3月に日本国籍を取ったんですよ。だから今は日本人」とレイリーさんは語る。戸籍名は門多路麗梨。美しい漢字名ですねと言うと、ありがとうと綺麗な笑顔を見せてくれる。しかし日本国籍を取るのは並大抵のことではなかったようだ。つまり日本の法務当局は外国人が日本国籍を取るのを敵視しているのかと思うほど手続きが煩雑で、しかも許可の要件が厳しい。
レイリーさん、実は国籍取得は2回目の手続きでできたもの。一度目は10年以上前で、このときは日本政府が要求したイラン国籍からの離脱証明をイラン政府が出してくれなかった。5年前に2回目の手続きを始めた。「とにかく書類が大変。それに家を見に来て近所の人に聞き込みはするなど、プライイベートなことをすごくチェックするし」。レイリーさんは親の財産証明を出せと言われて、親は親、私の問題とは関係ないとさすがにそれは拒否した。必要なのか必要でないのかわからないような書類が多いし、また何かにつけ細かな手続きが必要で、日本国籍取得はほかの人には勧められないわねえとレイリーさん。しかし「私にとってはふるさとだから」と決意は固かった。
通っていた学校はアメリカンスクールだったので日本語も英語も堪能だが、進路のことでは少し悩んだ。高校時代に陶芸を専門にやりたいと思ったが、これでは将来食べていくことは難しいと考え美術に方向転換した。おじが居たこともあって大学はイギリスに留学した。卒業後広告会社に就職し、13年前に独立した。当初一緒に独立した仲間と事務所を作ったが、やはり個性が強いもの同士うまく行かなかった。結局半年くらいでだめになり、それ以来1人で事務所を運営している。
会社案内からチラシ、名刺でも何でもデザインしますよと、レイリーさんは仕事への意欲を見せる。「例えば名刺はその人の顔にあたるでしょう。デザインが入るとぜんぜんイメージが違うんですよ」と小さなものでも熱意は同じだ。仕事をしているときが一番調子がいいというのは本当のようだ。
だから話は「大阪ガンバレ」ということになる。地盤沈下の激しい大阪。関西創業の企業も本社機能を東京に移すほどだ。しかし不況だからダメだと言っていては落ち込むだけ。大阪はソフトの部分に余りお金を使わないけれど、こういうときだからこそもっとソフトを重視し、独自の商品なりを開発すべきだと。そうするとデザインの仕事は本当に大事だと気づいてくれるんですけどねえと互いに妙に納得した。
明るい笑顔が絶えないレイリーさん。大阪市西区のちょっとクラシックなビルの1室から「仕事が元気のもと」とみんなを励ます声が聞こえてくる。
2001年6月キャリアアップを目指す:徐京淑さん
〜吉林省から青島・広州を経て上海へ・ 転職で仕事の内容を吸収
中国の学校は6月が卒業時期で、毎年100万人を超える大学卒業生が社会へと飛び立っていく。かつての社会主義経済時代には卒業生は「分配」と言う形で政府が仕事を決め、仕事にはあぶれないけれども必ずしも希望どおりの職につけなかった。現在ではそれが様変わりし、自ら売り込む形で就職しなければならなくなった。つきたい仕事につける反面、厳しい競争に勝ち抜かなければ将来の出世もない。
外資系企業が多数存在する上海ではより一層上昇を目指す若者が目立つ。彼らにとって企業はきちんと自分の能力を評価してくれるところでなければならず、逆に能力が評価されないとなると自分から見切りをつけ簡単に転職する。
徐京淑さん、31歳、中国の東北地方吉林省生まれ、朝鮮族の女性である。ハングル、日本語もこなす彼女は大学卒業後、いろいろ遍歴を経ていま上海の日系企業で働く。大都会の中で自らスキルアップを目指す一人の典型的な女性だとも言えるだろう。延辺大学で機械工学を学んだ徐さんは、卒業後国営企業でエンジニアとして働くが退職。青島で1年間で働いたのち、開放経済の先端の都市広州で行った。そこで日本向けの衣料を作っていた台湾の企業に就職する。ここで習い覚えた日本語を使うことになる。資料の作成や翻訳の仕事からはじめ、衣料品の生産についても習得していったが、5年経ったころに次のステップを目指し新たな仕事を探すことにした。
そして上海である。最初に就職したのは台湾系の企業。会社としての条件は良かったが、社長は指示をきちんと出さないわりには小さなミスを怒るばかりで、細かすぎた。だから4ヶ月で辞め次の会社に移った。次は上海人の女性が社長の貿易会社だったが、ここでも社長と合わなかった。これではストレスがたまり仕事を覚えるどころではないと、日系の会社に面接に行った。自分の求める仕事と会社あるいは社長の個人的な資質など、自分に会わないとわかればすぱっと辞めてしまう行動力は日本では考えられないだろう。
そして今の会社に入ったのが昨年8月である。日本の会社が注文するものにあわせて工場を探し、そこでの生産をチェックする。日本の会社は技術上の要求が厳しくてね、と言いながらも工場の生産した製品の質を厳しく判断する。会社を選ぶ基準は何ですかと聞くと、「もちろん仕事の内容、社長の人柄などがあるけど、やっぱり自分が伸びることができるかどうかじゃないかしら」ときっぱり答える。上海では公平・平等な評価を求めて転職するのはあたりまえ。また仕事以外で例えば語学の学校に通うとしてもそれはあくまで能力を伸ばし、給与・地位など評価の対象にするため、という人が多い。決して趣味や暇つぶしでお金を使うのではない。いささかドライすぎると感じられるかもしれないが、このきっぱりとした感覚は中国の若い世代に共通のものだろう。
「故郷へはいまべつに帰りたいとは思いません」と語る徐さん。上海での厳しい競争に勝ち抜いていくことができると当然信じている。
2001年4月インド家庭料理の店を経営:クンナさん
〜オリッサ州から日本へ・ 親切に接することがモットー
「いらっしゃい。今日のおすすめはチキンカレーですよ」と大きな声がよく通る。流暢な日本語でお客を迎え、いつも笑顔を絶やさない。それが繁盛の秘訣なのかもしれない。
笑顔の主は、大阪ミナミでインド家庭料理の店「サンタナ」を経営しているクンナさんだ。本名はシリカンタ・クマール・ダスで、ダスが姓。クマールは男という意味で、要するにシリカンタさんだが、なぜかみんなはクンナと呼ぶ。インドのオリッサ州にあるプーリーという町から来た。プーリーはインドの4大聖地の一つともなっており、ここに3昼夜滞在した人は輪廻転生から解脱できるとも言われ、ヒンドゥー教徒が数多く集まるので有名である。
今年30歳のクンナさんの実家はプーリーの町で「サンタナロッジ」という宿をやっている。40年以上の歴史があるが、西洋人のバックパッカーが来だしてから外国人が集まるようになり、日本人も増えてきた。今は3階建てで、60人くらいが泊まれる。店でも宣伝しているが1泊2食で300円という格安さだ。クンナさんはこんな環境に育ったことから、小さいときから日本を身近に感じていたと言う。旅行者から日本語も少しづつ教えてもらった。ある時よく泊まりにやってくる日本人が、そんなに日本に興味があるのならとクンナさんを日本に招待してくれた。それが91年のことである。3カ月日本に滞在し、東京や名古屋などあちこちに行って、ますます日本が気に入った。「何といっても日本人が私に親切だったことが印象に残りました」。
ある時宿にとまった日本人の女性が病気になり、クンナさんが病院に連れていったり、なにくれとなく世話をした。それが縁で彼女とつきあうようになり、結婚しようと思った。しかしクンナさんは五人兄妹の長男で、宿の跡継ぎと考えていた両親はこの結婚に大反対だった。結局親の了承も得ずにとにかく二人の生活を築こうと日本で生活することを決意したのである。
93年に来日。最初は神戸に住んで、飲み物やカレーを出す店「クンナ」を始めた。ところが震災でだめになって、一度失意の内にインドへ帰ったが、やはり好きな日本で暮らしたいとの気持ちは変わらず、再度来日した。結局本格的なインド料理の店を開いたらどうかということで、97年4月にいまの「サンタナ」を開いた。かつて父のホテルに泊まったことがある多くの日本人に開設を手伝ってもらった。「自分を支えてくれた人々には心から感謝しています」。そのためかクンナさん自身も故郷の地震に対して日本からカンパや衣類を送る活動をしている。「でも税関で税金を取るなんて言っててね。毎日国際電話で役所と交渉で怒鳴ってばっかしよ」とこの時ばかりはまじめな顔をした。
結婚に反対していた父だが、「サンタナ」と店を名付けたのもやはり故郷のことを思ったかもしれない、父は長男のクンナさんに早く帰ってきてほしいから、故郷では「あんな店は早くつぶれた方がいい」と言っているらしい。「素直に僕に直接言えばいいのにね」と語るクンナさんの顔には、憎めない親だな、という苦笑いが浮かんでいた。
2001年3月中国・西安で写真展を開催:細川和昭さん
〜明時代の民居の町・ 党家村に住む人々を撮る
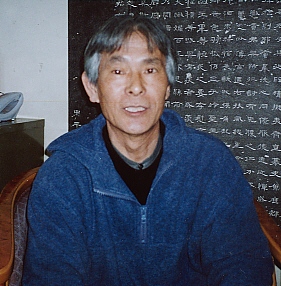
「高い壁に囲まれ、狭い路地があってと集落が凝集しているでしょう。いやあ、行ってみて面白いなと思って撮って、やっぱり面白いからまた行って撮ってと、結局3回村に通うことになりました」と語る写真家の細川和昭さん。細川さんが言う村とは中国陜西省にある党家村という集落で、明時代の建物・集落がほぼそのままの形で残っている所である。通い詰めて写真を撮って大阪でも発表したが、ひょんなことから中国でもやろうよと協力してくれる人がいて、陜西省の省都西安市で3月10日から16日まで写真展をおこなうことになったのである。いまはほぼ準備も終わりあとは出発するだけとなったけれど、果たしてどのくらいの人が見に来てくれるか一抹の不安はある。
細川さんは1940年大阪で生まれた。「もともとカメラマンを目指していたのではなく、ひょんなことから写真を撮るようになったんですよ」。もともと雑誌の編集をしていたが、編集会議の時にある写真に軽い程度のけちをつけたら、それならおまえ行って撮ってこいということになったそうだ。本格的にやりだしたのは出版社を辞めてからのことである。1975年フリーになってから宣伝ポスターを手がけたりしたが、一時川の写真をとりためていたことがある。淀川や大和川の上流から下流まで見て回って撮った。その一つの成果が「淀川の野草」という作品集である。
中国・党家村に撮りに行くきっかけとなったのは何ですかと聞くと、「関心を持っていたものがつながったということかな」と細川さんは語る。あるとき和歌山大学の先生に頼まれて雑賀崎の集落の写真を撮ったことがあって、それ以降面白いなと思う集落を撮っていた。それが中国の党家村に自然に繋がっていったということらしい。その延長かもしれないが、細川さんは中国の住居のひとつで、黄土高原地域に顕著な窰洞(ヤオトン)の村にも出かけている。「建築に興味があったというわけではなく、暮らしている人の生活のイメージを知りたかったんです」。厳寒の冬、都会に住む中国人でも行かない時に、それも夜にヤオトンの村に着いた。ちょうどそのとき雪が降って、本当に寒い村の風景が取れた。それが良かったのかもしれない。この村にもまた行って、ストーリーとして完結したいともことである。
中国・西安で日本の写真家が個人展を開くのはおそらく初めてだろう。自分の心を白紙にして、視界に入ってくるものを切り取る。それでいいんですよ、と明るく言い放つ細川さんの写真展が、西安の人々、党家村に住む地元の人にとってもニッコリとほほえむものになれば成功なのだろう。
2001年2月上海から友好の使者:郭盛麟さん
〜上海と大阪の交流へ・ 1年間の成果が実る

1年間大阪で過ごしてみて何を一番感じましたかとの問いに、「そうですね、日本人の考え方というのが感覚的なもので少し理解できるようになったということでしょうか」とまじめに答えた郭盛麟さんに、隣から「カラオケでたくさん唱ったことでしょう」と笑いとともに声がかかる。まあ楽しい生活を送ったことには違いがないだろう。
郭さんのいるのは大阪府日本中国友好協会の事務局である。大阪と上海市は府、市とも友好都市になっている関係で人的な交流も頻繁におこなわれている。郭さんは上海では上海市人民対外友好協会に努めており、日本に
来ることもたびたびだったが、大阪府日本中国友好協会との研修生派遣事業の一員として2000年4月1年間の予定で来阪した。
1959年生まれ上海で育った郭さん、小学校の時代に文化大革命の嵐にあった世代だ。小学1年の時はほとんど授業がなく、2年の後半からようやく始まったほどだ。「私が高等中学(日本の高校に相当)を卒業したときには、今みたいな大学入試がなかったんですよ」。だから郭さんは技術を身につけようと技術学校に入った。電気工業局に勤めながらラジオの日本語講座なんかを聴いて日本語に興味を抱いていたが、それが関係したのかどうか84年に上海市人民対外友好協会に転じた。ここでも郭さんの熱心さが発揮され、働きながら3年間上海外国語大学夜間大学で日本語を学んだ。
それが一つの財産になったのだろう、協会の日本処に籍を置いて日本と中国との友好活動を推進することになる。95年には半年間大阪府国際交流財団の招きで研修をおこなった。今回が2回目となったが、1年間という長期でありまた日中間の交流もより多様化していることもあり、前回とは比べものにならないほど忙しい日々を送った。
大阪府日本中国友好協会の研修生、大阪短期大学で日本文学を学ぶ学生の身分に加えて先生としての活動もあった。太成高校で週1回2時間だが中国語の授業を受け持ったのである。教えるのは楽しかったですよ、だって生徒は態度が良かったからね、と郭さん。それじゃあ態度が悪いところがあるんですかと尋ねれば、「今の大学生はね」と一言。やっぱり人の話を聞かないというのが大学生の評価になっているのかと思うと少々情けないような気もするが、中国から来ているから余計に感じるのかも知れない。
郭さんならカラオケという言葉がすぐ出てくるように(本人は強く否定したが)、歌はやっぱり好きとのこと。日本語を覚えるのに歌は有効な手だそうで良く唱うそうだ。「でも今どきの歌は唱えない。やはり演歌ですね」。踊るのも好き。中国の民歌も得意ですよと郭さん。そのほかに趣味はありますかと聞くと、切手収集は小さな時からおこなってきたとの返事が帰ってきた。
3月には上海に帰国する。妻と中学2年の女の子が待っているが、大阪でいろんな人と接することができたことは自分にとって大きな財産ですと語る郭さん、今後も日中の友好に尽くしたいとにこやかな笑顔を向けてくれた。
|